つる丸瓦版 リニューアル号
PDF版はこちらtsurumaru_201711.pdf
PDF版はこちらtsurumaru_201711.pdf
10月23日月曜日
台風の影響が残る中、晴れたのでミーティングを行いました。
今回は、年末商品の試食をしました。
☆野付ホタテ
直径3㌢弱で厚みも2㌢ほどあり、食べごたえありました。甘さもありとっても美味しかったです。
☆こんせんクリームケーキ
さっぱりした甘さのクリームで、ふわふわでお子さまも喜ぶ味だと思います。
☆伊達巻
あっさりした甘さで、食べやすいです。
☆ピッザ
直径15㌢の大きさクリスピータイプのピッザでです。
美味しい試食を試したり、地域での悩みごとなど楽しい会話に花を咲かせました!
こんなゆるい組合員活動です。
興味のある方は、お電話にてお伝えください。「ブログを見てくらぶ活動のミーティングの見学がしたい!」とお伝えいただければ、案内していただけます。
お問い合わせ:045(470)6863
( 月~金10時~17時)
エリア活動推進課迄、お待ちしています♪
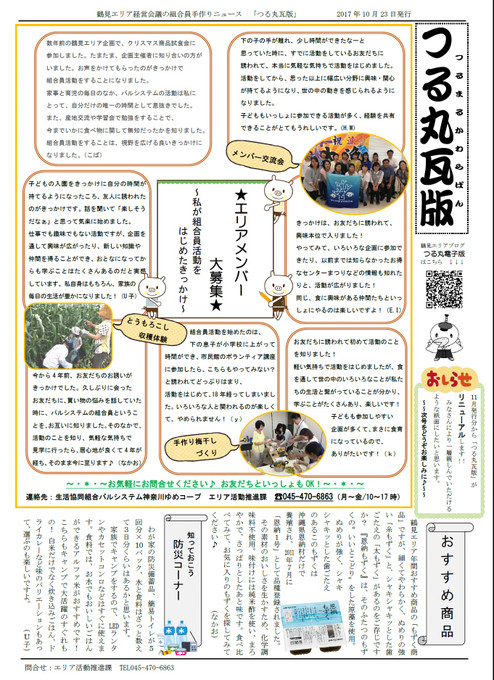 PDF版はこちら tsurumaru_201710.pdf
PDF版はこちら tsurumaru_201710.pdf
鶴見地区くらぶ うまうまyummyです。
先日、うまうまyummyに新たにメンバーが一人加わり、三人になりました。
そして、メンバーの共通点が、コーヒー大好き。
今日のミーティングでは、企画の話を進めていました。
子どもたちがプレイルームで、楽しそうに遊んでいる姿を見つつのミーティングです。
今日の試食は、
チョコ&パンプキンビスケット。ハロウィンフルーツラムネ。アンパンマンのおやさいせんべい。
お店にもハロウィン商品増えてきましたよね。我が家の子供たちも ハロウィンを楽しみにしている様子。
そんな うまうまyummy、小川珈琲株式会社さまにお願いして、コーヒーのこだわり、おいしい入れ方をおしえてもらうことにしました。
まだ募集は、先ですが、来年の2月6日(火曜日)に、鶴見センターにて開催予定ですので、ぜひご参加おまちしております。
次回のミーティングは、11月26日の日曜日の午前中にトレッサ横浜の師岡コミュニティハウスで行います。
ご興味のあるかたは、事前に地域支援課にお電話で「うまうまyummyのミーティングに参加したいです」とお伝えください。
お問い合わせ先 : 045-470-6863 地域支援課
宜しくお願いいたします。
9/25(月)ミーティングを行いました。仕事でこれないメンバーも居ましたが、先月は夏休みでミーティングをお休みにしたので久々に会えるのが新鮮でした!
今日の試食は、先週が涼しかったので注文したのがおでん種!!そろそろ、暖かいものが恋しくなってきたと思ったのですが、今日は思った以上に暑くなりましたので、冷房入れての試食となりました!
思った以上に量もあり、家族でも十分な量です!
大根皮をきんぴら風に炒めました。
こちらも、とても好評でした!
コーヒーにシホンケーキ、茹でた落花生などメンバーの持ちよりもあり、お腹一杯のミーティングになりました!
次回10/23(月)に鶴見センターにてミーティング行います。ご興味のあるかたは、事前に地域支援課にお電話で「Lucky!!のミーティングに参加したいです」とお伝えください。
お問い合わせ先 : 045-470-6863
(月~金10時~17時)
エリア活動推進課
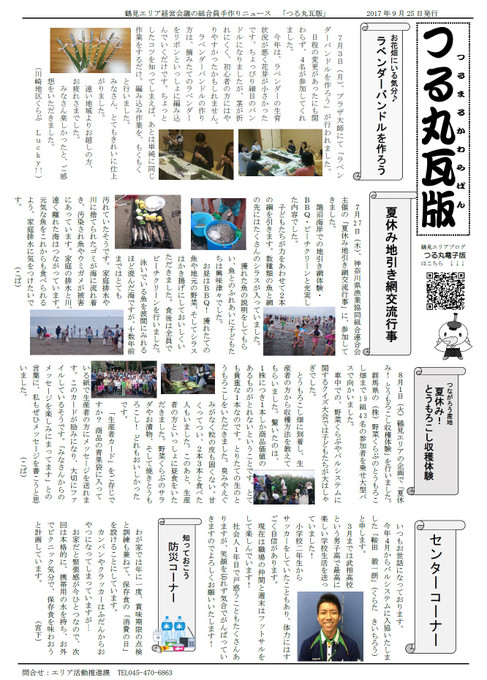 PDF版はこちらtsurumaru_201709.pdf
PDF版はこちらtsurumaru_201709.pdf
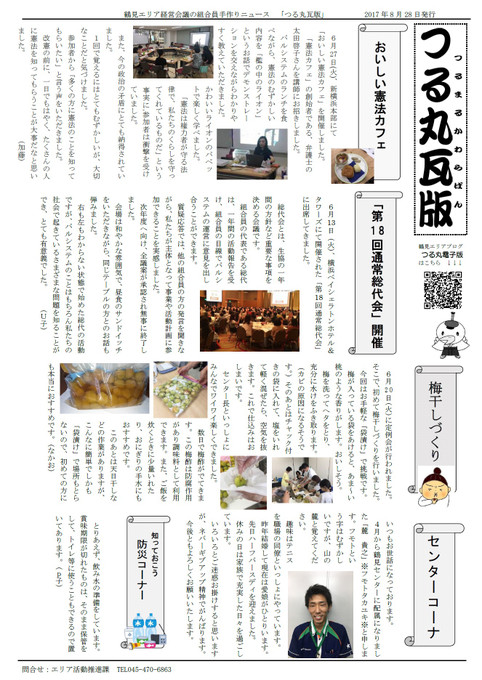 PDF版はこちらtsurumaru_201708.pdf
PDF版はこちらtsurumaru_201708.pdf
最近のコメント